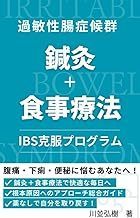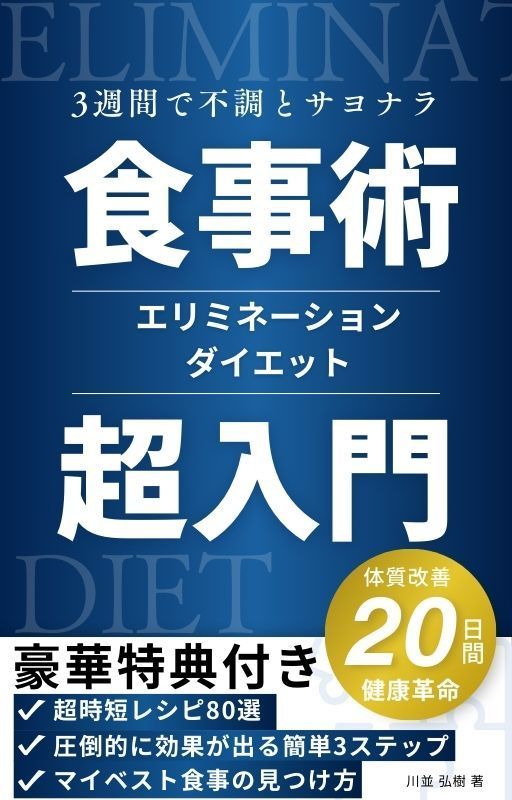「なんだか心が落ち着かない」
「理由もないのにドキドキする」
現代社会はストレスに溢れており、
もしかしたら、あなたもその一人かもしれません。
「不安」という感情は、
しかし、その不安が長く続いたり、
この記事では、東洋医学の視点から、この厄介な「不安感」
これまで西洋医学的な視点しか知らなかった方も、
そして、不安感を和らげ、
え?不安って身体のせい?東洋医学がみる不安感のメカニズム
西洋医学では、不安感は脳内の神経伝達物質のバランスの乱れや、
もちろん、これらの生理学的なメカニズムも非常に重要です。
しかし、東洋医学では、不安感を単なる「心の状態」
私たちの体には、「気(き)」「血(けつ)」「津液(しんえき)
- 気(き): 生命エネルギーであり、体を動かす力、内臓の働き、
精神活動などを支えます。 - 血(けつ): 全身に栄養を運び、心身を潤し、
精神を安定させる働きがあります。。 - 津液(しんえき): 体に必要な水分で、血液以外の体液全般を指します。
東洋医学では、これらの要素がスムーズに体内を巡り、
一方、ストレスや不規則な生活、食生活の乱れなどによって、
例えば、
- 気の不足(気虚:ききょ): エネルギーが不足することで、心身ともに活力が低下し、
些細なことにも不安を感じやすくなります。「 なんだか疲れやすいのに、神経だけが高ぶる」といった状態も、 気の不足からくる場合があります。
- 気の上逆(きの上衝:きのじょうしょう): 本来、下に向かうべき気が逆方向に上昇することで、
動悸や息苦しさ、イライラ感、 そして不安感を引き起こすことがあります。「 胸がドキドキして落ち着かない」といった症状は、 気の上逆が関与しているかもしれません。
- 血の不足(血虚:けっきょ): 体を栄養する血が不足すると、精神的な安定感が失われ、
不安や憂うつ感を感じやすくなります。「眠りが浅い」「 顔色が悪い」といった症状も、 血の不足と関連することがあります。
- 津液の滞り(痰飲:たんいん): 体内の水分代謝がうまくいかず、余分な水分が滞ると、
めまいや頭重感、そして精神的な不安定さを招くことがあります。 「頭がスッキリしない」「気分が重い」と感じる場合、 津液の滞りが影響しているかもしれません。
このように、東洋医学では、
放っておくと大変!不安感が引き起こす悪循環
「まあ、よくあることだから…」と、
不安感は、私たちの心と体に様々な悪影響を及ぼし、
1. 身体的な不調:
- 自律神経の乱れ: 不安感が続くと、自律神経のバランスが崩れやすくなります。
これにより、動悸、息切れ、めまい、頭痛、胃腸の不調、 発汗など、様々な身体症状が現れることがあります。 - 免疫力の低下: ストレスは免疫力を低下させることが知られています。
慢性的な不安感も同様に、免疫機能を低下させ、 風邪や感染症にかかりやすくなる可能性があります。 - 睡眠の質の低下: 寝る前に不安を感じると、なかなか寝付けなかったり、
夜中に何度も目が覚めたりと、睡眠の質が著しく低下します。 質の悪い睡眠は、心身の疲労回復を妨げ、 さらに不安感を増幅させる悪循環を生み出します。
2. 精神的な不調:
- 集中力・記憶力の低下: 不安に心が囚われると、目の前のことに集中できなくなり、
物忘れもしやすくなります。仕事や勉強の効率が低下し、 さらに自己嫌悪に陥る可能性もあります。 - イライラや怒りっぽくなる: 慢性的な不安感は、心の余裕を奪い、
些細なことにもイライラしたり、 怒りっぽくなったりすることがあります。これは、 人間関係にも悪影響を及ぼしかねません。 - うつ病のリスクを高める: 長期間にわたる強い不安感は、
うつ病の発症リスクを高めることが指摘されています。
このように、不安感は単なる一時的な感情の揺れ動きではなく、
だからこそ、早めにそのサインに気づき、
東洋医学からの処方箋:
では、東洋医学では、
ここでは、
1. 食養生:体の中から「安心」を育む
「食は人の基本」という考え方は、
- 補気(ほき)食材: エネルギーを補い、精神的な安定を促す食材として、米、麦、
豆類、山芋、きのこ類、鶏肉などがあります。
- 補血(ほけつ)食材: 血を補い、心の栄養となる食材として、レバー、ほうれん草、
プルーン、黒ごま、ひじきなどがあります。
- 安神(あんじん)食材: 精神を安定させる効果が期待できる食材として、ナツメ、菊花、
ハーブティー(カモミール、ラベンダーなど)などがあります。
一方で、過剰な刺激物や消化に悪いものは避けるようにしましょう
カフェインやアルコール、脂っこい食事、甘いものの摂りすぎは、
2. 養生法:日々の習慣で「安定感」を積み重ねる
日々の生活習慣を見直すことも、
- 質の良い睡眠: 毎日同じ時間に寝起きし、十分な睡眠時間を確保しましょう。
寝る前のスマートフォンやパソコンの使用は控え、 リラックスできる環境を整えることが大切です。
- 適度な運動: 軽いウォーキングやストレッチなど、
無理のない範囲で体を動かすことは、気の巡りを良くし、 心身のリフレッシュにつながります。
- 深呼吸: 意識的にゆっくりと深い呼吸をすることは、自律神経を整え、
心を落ち着かせる効果があります。不安を感じた時や、 寝る前などに行うと良いでしょう。
- リラックスできる時間: 音楽を聴いたり、お風呂にゆっくり浸かったり、
趣味に没頭したりするなど、 自分にとって心地よいリラックスできる時間を持つようにしましょ う。
3. 東洋医学的なアプローチ:専門家の力を借りる
東洋医学には、鍼灸や漢方薬、按摩(あんま)など、
- 鍼灸(しんきゅう): 体の特定のツボを刺激することで、気の巡りを改善し、
心身のバランスを整えます。
- 漢方薬(かんぽうやく): 生薬を組み合わせた漢方薬は、体全体のバランスを整え、
根本的な体質改善を目指します。
- 按摩(あんま): 体の筋肉を緩めることで、血行を促進し、
心身のリラックスを促します。
もし、長引く不安感に悩んでいる場合は、自己判断せずに、
まとめ:東洋医学の知恵で、穏やかな心を取り戻しましょう
この記事では、東洋医学の視点から不安感の原因と悪影響、
不安感は、決して心の弱い人が陥るものではありません。
ストレス社会で生きる私たちにとって、
しかし、その不安感が長く続く場合は、
東洋医学の知恵を借りれば、体全体のバランスを整えることで、
今日からできる食養生や養生法をぜひ実践してみてください。
そして、もし専門的なサポートが必要だと感じたら、
あなたの心が、穏やかで健やかな日々を送れるよう、