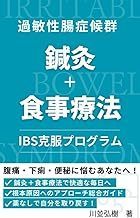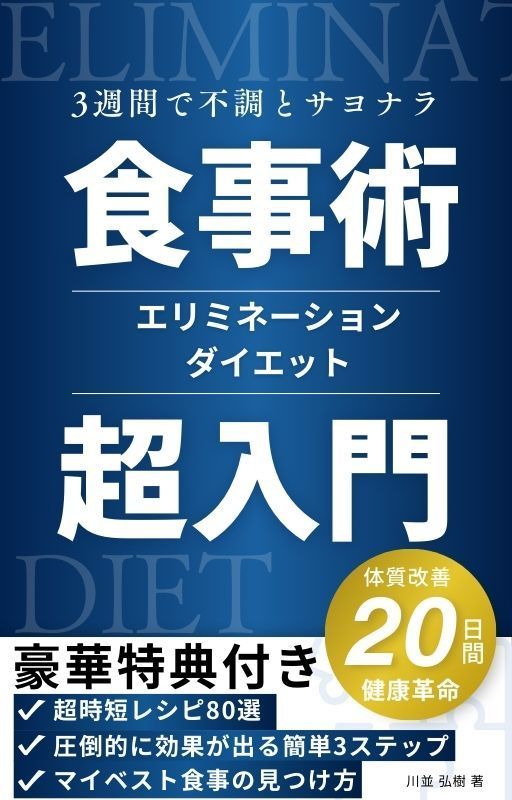「あれ?私、昔はこんなに疲れやすかったっけ?」
ふと、そんな疑問が頭をよぎることはありませんか?
20代、30代の頃は、
鏡を見るたび、「老けたな」と感じるだけでなく、
家事をこなすのもやっとで、
娘さんの「今日の晩ごはん、これ?」という言葉に、
この「しんどい」ループから抜け出したいけれど、
もしかしたら、その疲れには、
その「わけもなく疲れる」状態、もしかして「
病院で検査しても「異常なし」と言われるのに、
「ホルモンって、女性ホルモンのことでしょ?」
もちろんその通りですが、
そして、
40代女性に多い「プレ更年期」とは?
「更年期」と聞くと、もっと先の世代の話だと思っていませんか?
実は、女性ホルモンの分泌は、
これが「プレ更年期(更年期移行期)」と呼ばれる時期です。
まだ生理が順調でも、ホルモンバランスは少しずつ変化しており、
特に、
ホルモンバランスが乱れると、体はどうなる?
ホルモンは、体の様々な機能の「指揮者」
この指揮者の指示が乱れると、体中のシステムが混乱し、
1. 自律神経の乱れと疲労感
エストロゲンの減少は、
・睡眠の質の低下:
寝つきが悪くなる、夜中に何度も目が覚める、
・体温調節の不調:
ホットフラッシュ(急なほてりや発汗)や、
・心身の不安定さ:
常に緊張状態になったり、反対にだるさが抜けなかったりします。
2. エネルギー代謝の低下
ホルモンは、体のエネルギー代謝にも深く関与しています。
ホルモンバランスが乱れると、
3. 精神的な不調
女性ホルモンの変動は、
4. 身体的な変化とそれに伴う疲労感
ホルモンバランスの乱れは、
・PMS(月経前症候群)の悪化: 月経前に特に体のだるさ、むくみ、頭痛、
・肩こり・頭痛: 血行不良や自律神経の乱れから、
・関節の痛み: ホルモン変動が関節の健康にも影響を与えることがあります。
「私、ホルモンバランス乱れてる?」セルフチェック
以下の項目に当てはまるものが多い場合、
・生理周期が不規則になったり、経血量が変わったりした?
・以前より汗をかきやすくなった、
・寝つきが悪くなった、夜中に何度も目が覚める?
・些細なことでイライラしたり、
・疲れているのに、疲労感が翌日に持ち越されるようになった?
・首や肩のこりがひどくなった、または頭痛が増えた?
・やる気が出ない、集中力が続かないと感じることが多い?
もし心当たりがあるなら、
ホルモンバランスを整えて、元気を取り戻す方法
ホルモンバランスを整えるには、薬に頼るだけでなく、
1. 鍼灸で心身のバランスを整える
「鍼灸でホルモンバランスが整うの?」
東洋医学では、体の不調は「気(エネルギー)」「血(
・自律神経の調整:
鍼やお灸による適切なツボへの刺激は、
・血流の改善:
鍼灸は全身の血流を促進します。血流が改善されることで、
・内臓機能の向上:
東洋医学の観点から、ホルモンバランスは「肝(かん)」「腎(
・睡眠の質の向上:
自律神経が整い、体がリラックスすることで、
このように、鍼灸は直接的なホルモン補充療法ではありませんが、
2. 質の良い睡眠を確保する
睡眠は、ホルモン分泌や自律神経の調整に最も重要です。
・毎日決まった時間に寝起きする: 体内時計を整え、ホルモンリズムを安定させます。
・寝る前のスマホやPCは控える: ブルーライトは睡眠ホルモンの分泌を妨げます。
・リラックスできる環境作り: 寝室を暗く静かにする、アロマを焚く、
・ぬるめのお風呂: 就寝1~2時間前に38~40℃
3. バランスの取れた食事を心がける
特定の食品だけでなく、
・良質なタンパク質: ホルモンや神経伝達物質の材料になります(肉、魚、卵、
・ビタミンB群: エネルギー代謝や神経機能に不可欠(全粒穀物、レバー、
・ビタミンD: ホルモン調整や精神の安定に重要。日光を浴びるか、サケ、
・マグネシウム: 神経の興奮を抑え、リラックス効果、睡眠の質向上に役立ちます(
・大豆製品: 大豆イソフラボンは、女性ホルモン(エストロゲン)
・不飽和脂肪酸: ホルモン合成の材料になります(青魚、アマニ油、えごま油など)
4. 適度な運動を取り入れる
無理のない範囲で、体を動かす習慣を持ちましょう。
・ウォーキング、ヨガ、ストレッチ: 軽い運動は血行を促進し、自律神経を整え、
・短時間でも毎日続ける: 「毎日30分」と決めなくても、「15分だけ歩く」「
5. ストレスを上手に管理する
ストレスはホルモンバランスを乱す大きな要因です。
・趣味やリラックスできる時間を持つ: 自分の好きなことに没頭する時間を作る。
・アロマテラピーや瞑想: 心を落ち着かせ、リラックス効果を高めます。
・友人との会話: 悩みを共有したり、
・完璧主義を手放す: 「全部自分でやらなきゃ」という思い込みを手放し、
6. 必要に応じて専門家に相談する
セルフケアでも改善が見られない場合は、
まとめ
「異常なし」と言われても続く疲労感。その影には、
今日から、鍼灸を含む質の良い睡眠、バランスの取れた食事、
もし、この記事を読んで「もしかして私も?」と感じたら、