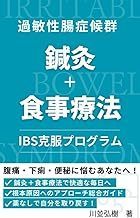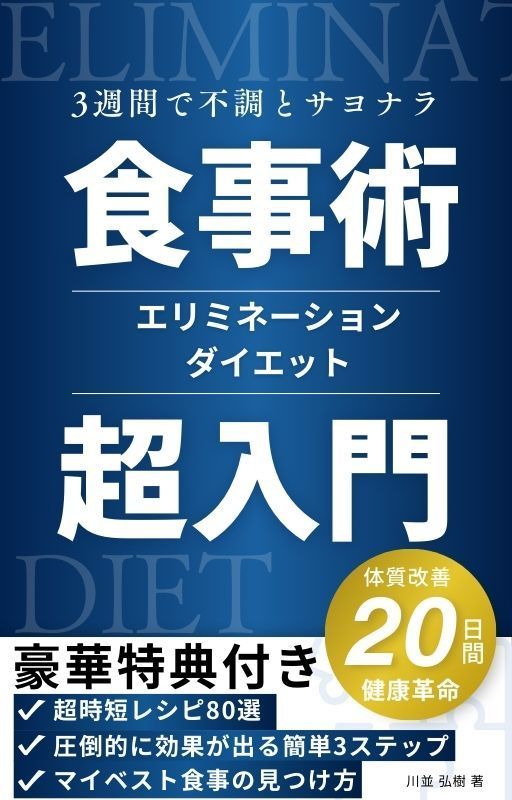関節リウマチ、橋本病、潰瘍性大腸炎…。
異なる病気でも、不思議と患者さんの言葉には共通点があります。
それは「薬だけでは届かない不調」があるということ。
会話でひも解く「なぜ症状が残るのか?」
患者さんA(関節リウマチ)
「先生、薬を飲んでいるんですけど…朝の手のこわばりが全然よくならなくて。数値は落ち着いてるって言われるんですけど、生活がつらいんです」
私:「なるほど。それはよくあるご相談です。実は“数値には現れない部分”が関係していることが多いんですよ」
患者さんA:「数値に出ない…?それって何ですか?」
私:「それが、自律神経の乱れなんです」
自律神経と免疫の深い関係
患者さんB(橋本病)
「自律神経って、よく聞くけど正直ピンと来ないです。免疫と関係あるんですか?」
私:「はい。交感神経は“活動モード”、副交感神経は“休息モード”と考えてください」
患者さんB:「ふむふむ」
私:「交感神経が強く働くと炎症や免疫反応が高まりやすいんです。逆に副交感神経が働くと炎症が落ち着き、体が回復しやすくなる。だから自律神経が乱れると、炎症や不調がいつまでも続くことがあるんです」
♂️ 患者さんC(潰瘍性大腸炎)のケース
患者さんC
「僕は潰瘍性大腸炎なんですが、ストレスが溜まると必ずお腹の調子が悪くなるんです。薬を飲んでいても、仕事が忙しい時期は下痢や腹痛がひどくなります」
私:「まさにそれも自律神経が関係しています。強いストレスがかかると交感神経が過剰に働き、腸の炎症が悪化しやすいんです」
患者さんC:「確かに、大事な会議のあとに悪くなることが多いです」
私:「そうでしょう?逆に副交感神経が整うと腸の働きは落ち着きやすくなります。だから“自律神経のバランスを整える”ことが、潰瘍性大腸炎の症状を和らげるポイントになるんですよ」
患者さんC:「薬では抑えきれない部分が、自律神経に隠れているんですね」
セルフケア①:ツボ押し
私:「ではここで、自律神経を整えるのに役立つツボをいくつかご紹介します」
- 内関(ないかん):手首の内側、しわから指3本分下。不安や胸のつかえをやわらげる。
- 足三里(あしさんり):膝の外側、すねの骨の下。胃腸を整え、免疫力や体力をサポート。
- 三陰交(さんいんこう):内くるぶしから指4本分上。ホルモンや免疫のバランスを調える。
ポイント
呼吸に合わせてやさしく1〜2分押すだけでOK。リラックスしながら行うのが効果的です。
セルフケア②:食事と薬膳
患者さんB:「食事でできることってありますか?」
私:「もちろんあります。腸を整えることが免疫と自律神経の安定に直結します」
✅ 積極的にとりたいもの
- 発酵食品(納豆、味噌、ヨーグルト)
- 大豆製品(豆腐、豆乳)
- 青魚・亜麻仁油(炎症を和らげるオメガ3)
- 海藻類(わかめ、昆布)でミネラル補給
薬膳的におすすめ
- 梨・れんこん:潤いを与え、炎症を鎮める
- セロリ:イライラや頭痛を落ち着ける
- 大根:消化を助け、上がった気を下げる
気持ちを上げる食材(気を巡らせる食材)
- みかん・柑橘類:香りで気の巡りを良くし、気分を晴れやかにする
- しそ(紫蘇):香りが心を落ち着け、不安感を和らげる
- バジル・ミント:気をスーッと巡らせ、リフレッシュさせる
代謝を良くする食材(温めてエネルギーを補う食材)
- 生姜:体を温め、血流を促し代謝を上げる
- ねぎ:体を温め、冷えを改善してエネルギーを補う
- にんにく:胃腸を温め、気力を高める
- 黒ごま:腎を養い、代謝やホルモンのバランスを整える
控えたいもの
- 白砂糖の多いお菓子
- カフェイン飲料(コーヒー、エナジードリンク)
- アルコール
- 加工食品やジャンクフード
患者さんC:「梨やれんこんって手軽に取り入れられそうですね」
私:「そうですね。ちょっとした工夫でも、体は必ず応えてくれます」
セルフケア③:習慣の工夫
患者さんA:「ツボや食事以外で、生活習慣でできることはありますか?」
私:「はい。特別なことではなく、毎日の習慣を少し整えるだけで大きな効果があります」
- 朝日を浴びて体内時計をリセットする
- 深呼吸や瞑想で副交感神経を優位にする
- 軽い運動(散歩・ストレッチ)で血流を促す
- 睡眠のリズムを一定に保つ
小さな積み重ねが大切
難しいことをする必要はありません。日常の工夫だけで、自律神経と免疫は確実に安定していきます。
✨ まとめ
関節リウマチ、橋本病、潰瘍性大腸炎――異なる病気であっても、共通しているのは 「自律神経の乱れ」 です。
- Aさん(関節リウマチ) → 痛みやこわばりが強まる背景に交感神経の過剰
- Bさん(橋本病) → 代謝低下や気分の落ち込みと自律神経の切り替え不良
- Cさん(潰瘍性大腸炎) → ストレスで腸の炎症が悪化
薬は大切ですが、それだけでは届きにくい領域があります。
ツボ押し、食事、習慣といった日常の工夫が、自律神経を整え「数値には現れない不調」を和らげる大きな一歩になります。