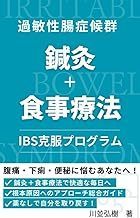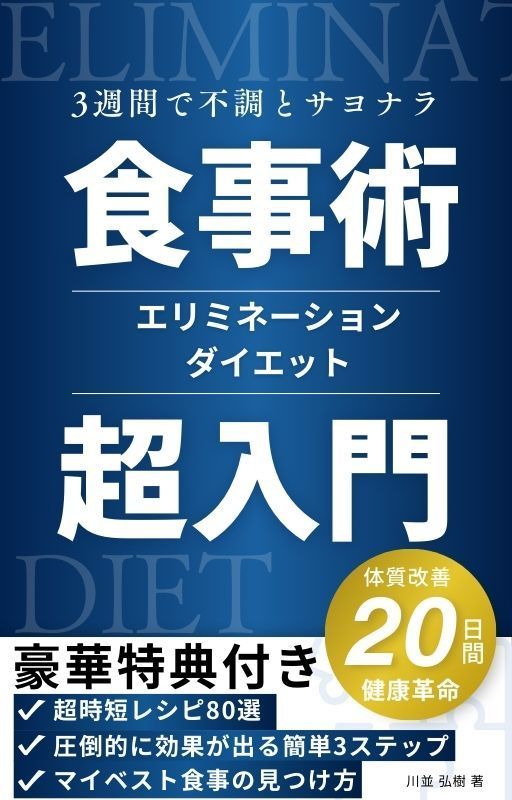〜東洋医学が教える「気・血・水」の季節バランス〜
季節の変わり目になると、なぜか体がだるい、眠い、やる気が出ない。
そんな経験はありませんか?
東洋医学では、季節の変化=体のエネルギーの変化と考えます。
気温・湿度・気圧・日照時間が変わるたびに、
体の中の「気・血・水」の流れも揺らぎます。
つまり、季節の不調は「体質の問題」ではなく、
環境への“適応力”が弱っているサインなのです。
春:肝の季節——気の巡りをスムーズに
春は自然界で“気”が上に昇る季節。
人の体も同じように、エネルギーが外向きに動き始めます。
しかし、冬の間にため込んだストレスや冷えが残っていると、
この上昇の流れにブレーキがかかり、
イライラ、頭痛、肩こり、めまいなど「気滞(きたい)」が起こりやすくなります。
【おすすめセルフケア】
・朝の深呼吸や軽いストレッチで、気の巡りを促す
・食事は香りのある食材(しそ、セロリ、みょうが、ゆず)を意識
・パソコン作業が多い人は目を休める時間をつくる
特に、春は「頑張りすぎて疲れる」人が多い季節。
予定を詰めすぎず、“余白”をつくることが肝を整える第一歩です。
梅雨:脾の季節——湿をためない
梅雨は湿気が多く、体の中にも「湿(しつ)」がこもりやすくなります。
東洋医学ではこの状態を「水滞(すいたい)」と呼び、
むくみ、胃もたれ、頭の重さ、だるさ、気分の沈みなどを引き起こします。
【おすすめセルフケア】
・温かい飲み物を選び、冷たいものを避ける
・食事には利水作用のあるハトムギ・小豆・冬瓜を取り入れる
・朝、白湯を飲んで体の“内側の湿”を流す
そして、湿を抜くには「脾」を守ることが大切です。
脾は消化吸収を司る臓腑で、冷えとストレスに弱い傾向があります。
腹八分目とゆっくりした食事が、脾を守る基本になります。
秋:肺の季節——呼吸で“気”を調える
秋は空気が乾燥し、肺の働きが乱れやすくなる時期です。
東洋医学では、肺は「気」をコントロールする臓腑とされています。
肺が弱ると、
・息が浅くなる
・免疫力が下がる
・肌や喉が乾燥する
・気分が落ち込みやすくなる
といった不調が現れます。
【おすすめセルフケア】
・深い呼吸を意識する(4秒吸って、8秒吐く)
・白い食材(大根、れんこん、長ねぎ、豆腐、梨)を取り入れる
・早寝早起きで生活リズムを整える
呼吸は「気」を養う最もシンプルな方法です。
忙しい日ほど、1日3回だけでも“呼吸を感じる時間”を持ちましょう。
冬:腎の季節——体を温め、エネルギーを蓄える
冬は自然界のエネルギーが“内側に沈む”季節。
体も同じように、外に出すより内に“ためる力”が大切になります。
腎は生命エネルギーの源。
ここが弱ると、冷え、腰痛、むくみ、疲労感、不眠などが起こりやすくなります。
【おすすめセルフケア】
・下半身を冷やさない(特に腰と足首)
・黒い食材(黒豆、黒ごま、ひじき、海苔)で腎を補う
・夜は23時前に寝て、エネルギーを蓄える
また、腎を守るには「静けさ」が必要です。
冬は無理に活動を増やさず、
“立ち止まる勇気”を持つことで、春からの動きが軽くなります。
季節ごとに変化する「気・血・水」
・春 → 気が上に昇る → ストレスに注意
・梅雨 → 水が滞る → 湿と冷えに注意
・秋 → 肺が乾く → 呼吸と保湿に注意
・冬 → 腎が弱る → 冷えと睡眠不足に注意
このサイクルを知っているだけで、
「季節の不調」に予防的に対応できるようになります。
まとめ
季節に合わせて体を整えることは、
“自然と調和して生きる”という東洋医学の基本です。
・春は気を巡らせ、
・梅雨は湿をさばき、
・秋は気を養い、
・冬は腎を温める。
この4つの流れを意識することで、
1年を通して体調が安定し、天気や環境の変化に振り回されにくくなります。
体は自然の一部。
だからこそ、季節の流れを味方につけることが、
最高のセルフケアになるのです。