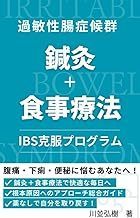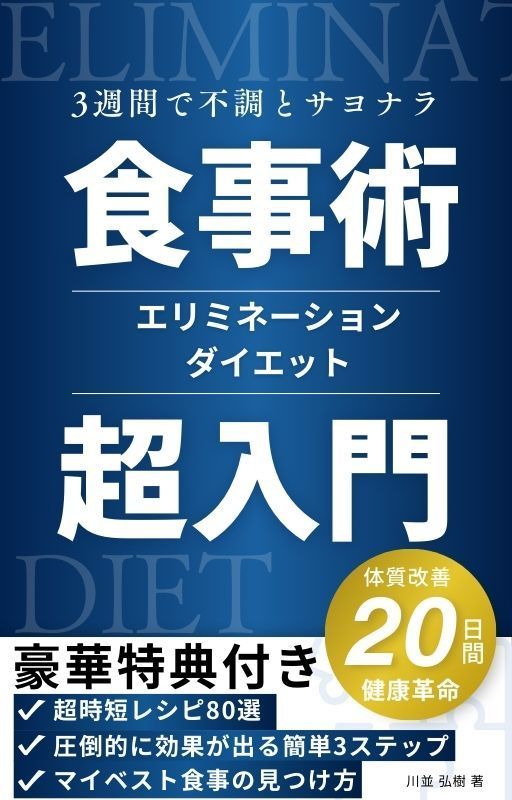「ちゃんと寝たのに、朝から疲れている」
「コーヒーを飲まないと頭が働かない」
「夕方になると集中できない」
そんな毎日が続いていませんか?
それは“気のせい”でも“根性不足”でもなく、
あなたの体を支える小さな臓器――「副腎」が疲れているサインかもしれません。
副腎は、ストレスや血糖値の変化など、
あらゆる刺激から体を守る“司令塔”のような存在。
しかし、現代の忙しさやプレッシャーの中で、
休む間もなく働き続け、やがて燃え尽きてしまいます。
この記事では、
朝からエネルギーを取り戻すための「副腎を休ませる3つの習慣」を、
東洋医学と栄養学の両面からわかりやすく解説します。
朝のスイッチ:コルチゾール
朝、体が自然に目を覚ますのは、
コルチゾール(ストレスホルモン)が分泌されるからです。
本来、コルチゾールは夜に下がり、朝に上がるように設計されています。
これが「体内の朝スイッチ」。
しかし、夜更かしや過度なストレスが続くと、
夜になってもコルチゾールが下がらず、
結果として「眠れない→翌朝も上がらない」という悪循環に。
この状態では、朝の目覚めが悪く、
日中の集中力・気力も低下します。
→夜のスマホ・強い光・寝酒は、すべてこの“コルチゾールリズム”を乱す要因になります。
日中の安定:セロトニン
セロトニンは、心を安定させるホルモンであり、
「幸福ホルモン」とも呼ばれます。
朝の光を浴びることで分泌が始まり、
日中の気分・集中力・姿勢の安定を支えています。
さらに大切なのは、
このセロトニンが夜になるとメラトニン(眠りのホルモン)に変化するということ。
つまり、
朝に光を浴びてセロトニンを出せなければ、
夜にメラトニンが作られず、自然な眠気が起こりにくくなります。
→ 「良い眠り」は、実は朝から始まっているのです。
夜の静寂:メラトニン
メラトニンは、暗くなると分泌が始まり、
体温・血圧・脈拍を下げ、眠りのスイッチを入れます。
ただし、スマホやパソコンのブルーライト、
強い照明の光は、脳に「まだ昼だ」と錯覚させ、
メラトニンの分泌を遅らせてしまいます。
その結果、寝つきが悪く、睡眠が浅くなる。
つまり、“夜の光”が“体内時計”を後ろにずらしてしまうのです。
→ 寝る1時間前は「光を減らす」ことが、何よりも効果的な睡眠薬。
東洋医学でみる「脳とホルモン」
東洋医学では、ホルモンバランスの乱れを
「肝」と「腎」の不調として捉えます。
- 肝(かん):気血の流れを司り、情緒を安定させる
- 腎(じん):生命エネルギー(精)を蓄え、睡眠と回復を支える
夜の過剰なストレスや考えすぎは「肝の気滞(きたい)」、
疲労の蓄積や冷えは「腎虚(じんきょ)」を招き、
結果として眠りとホルモンのバランスを崩します。
対策としては、
- 寝る前の足湯で「腎」を温める
- 深呼吸で「肝」の滞りを流す
- 足三里・三陰交へのお灸で全身の巡りを整える
といったケアが効果的です。
まとめ:眠りの質は「1日のリズム」で決まる
眠れない夜を変えるために、
夜の行動だけを変えるのは実は逆効果。
「朝に光を浴びる」
「日中に動く」
「夜は光を減らす」
この3つのリズムを整えることで、
メラトニン・セロトニン・コルチゾールが自然に連動し、深く安らかな眠りが戻ってきます。