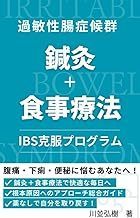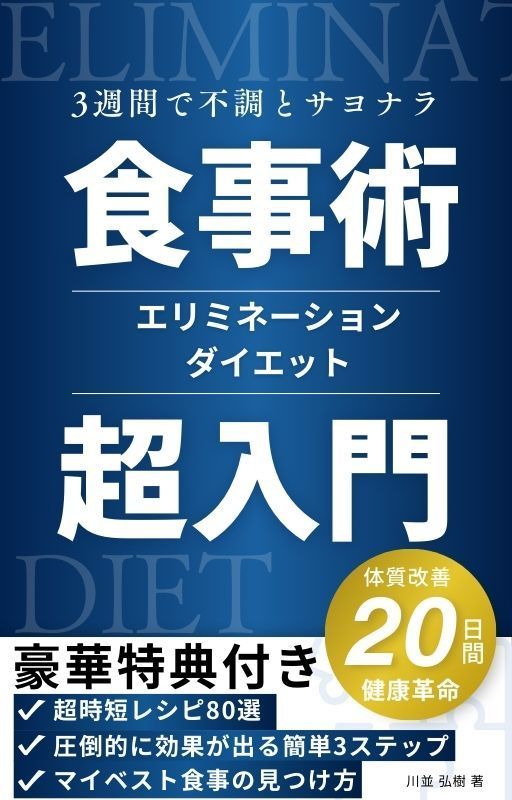1. 朝日を浴びる(光で脳をリセット)
セロトニンは、「光」によってスイッチが入ります。
朝、太陽の光が目の奥の網膜に届くと、脳の“視交叉上核”が刺激され、
体内時計がリセットされます。
この刺激によって、
「メラトニンの分泌が止まり、セロトニンが活性化」します。
つまり、光は“朝をつくる薬”のような存在なのです。
☀️ 朝起きたらまずカーテンを開けて日光を浴びる。
それだけで自律神経の切り替えがスムーズになり、
1日のスタートが整います。
曇りの日でも効果あり。
屋外の光は室内照明の10倍以上の明るさがあります。
♀️ 2. 朝のリズム運動(体を動かしてセロトニンを増やす)
セロトニンは、一定のリズム運動で分泌が高まります。
代表的なのが、
- ウォーキング
- 深呼吸
- 軽いストレッチ
- 朝の掃除や片付け
ポイントは「呼吸と動きを合わせること」。
例えば、ゆっくり息を吸いながら伸びをし、
吐きながら肩を回す──それだけでも脳が“安心モード”になります。
たった5分のリズム運動でも、セロトニンはしっかり活性化します。
朝の「動」と「呼吸」は、脳にとって最高の目覚ましです。
3. 朝食でトリプトファンを摂る
セロトニンは、食事から作られます。
その材料となるのがトリプトファンというアミノ酸。
トリプトファンを多く含む食品は、
納豆・豆腐・味噌・卵・バナナ・青魚など。
ただし、トリプトファン単体では脳に届きにくいため、
糖質+ビタミンB6と一緒に摂ることがポイント。
たとえば朝食に:
ご飯+味噌汁+卵+納豆
オートミール+ヨーグルト+バナナ
この組み合わせで、セロトニンが日中しっかり作られ、
夜には自然な眠気をもたらす「メラトニン」へと変化します。
東洋医学からみた「朝のセロトニン」
東洋医学では、朝の時間帯は「陽気(ようき)」が上昇し始める時。
この“陽気の立ち上がり”が鈍いと、
日中のエネルギー不足や気分の停滞が起こります。
つまり、セロトニンが不足している状態は、
東洋医学的に言えば「気虚(ききょ)」や「気滞(きたい)」と似ています。
対策:
- 朝に白湯を飲み、内臓をゆっくり目覚めさせる
- 深呼吸で「気」を巡らせる
- 足三里へのお灸で朝のエネルギーを底上げ
「気を動かす=セロトニンを動かす」と考えると、
東洋医学と脳科学は実はとても近いのです。
✨ まとめ:朝5分のリズムが夜を変える
眠れない夜を変えたいなら、
夜の工夫よりも朝のセロトニン習慣を整えること。
1️⃣ 朝の光を浴びる
2️⃣ 体をゆっくり動かす
3️⃣ 朝食でトリプトファンを摂る
この3つを「できる範囲」で続けるだけで、
脳のホルモンリズムが整い、眠りの質・気分の安定・集中力まで改善します。